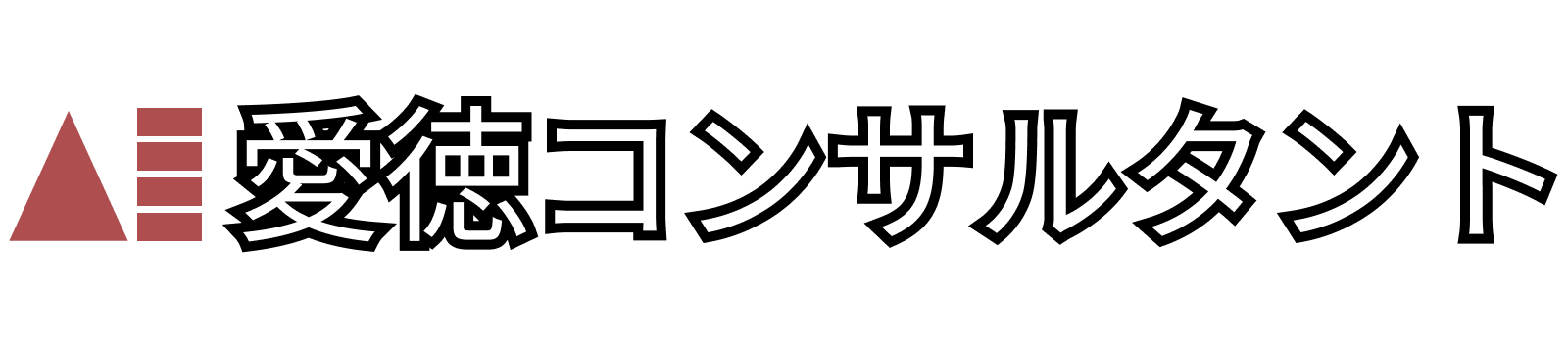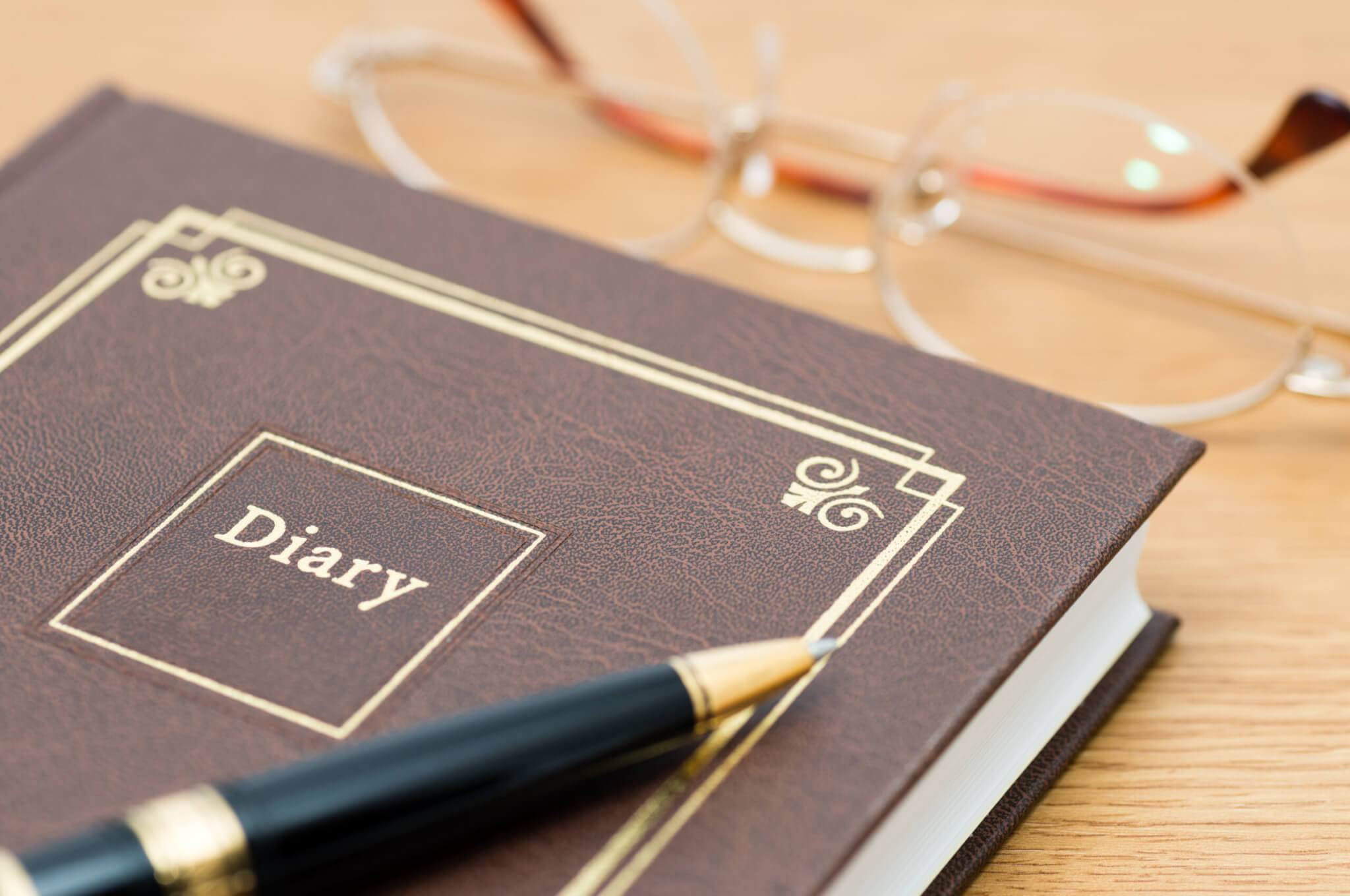2025年、私は**一般社団法人日本非破壊検査協会(JSNDT)**が実施する「赤外線サーモグラフィ試験 レベル1」に合格しました。
この資格は、非破壊検査の一手法である赤外線サーモグラフィを正しく理解し
基本的な撮影・解析・報告ができる技術者として認定されるもので、
インフラ点検における非常に重要な第一歩となります。
インフラの老朽化がもたらす社会課題
私がこの資格を目指すことになった最大の理由は、日本の社会資本の老朽化問題です。
高度経済成長期に整備された道路、橋梁、トンネル、上下水道などのインフラは、今後一気に“築50年超”となるものが増加します。
国土交通省の発表によると、今後10年間で建設後50年以上が経過する社会資本の割合は急増し
それに伴い維持管理・更新費用も増加の一途をたどるとされています。
実際、国の予算においても、「インフラメンテナンス」分野に多くの予算が確保されつつあり、
公共事業の重点施策の一つに位置付けられています。
そんな中、構造物の健全性を非破壊で評価できる赤外線サーモグラフィ技術が、インフラ点検分野で注目を集めています。
サーモグラフィ技術とは?その役割と可能性
赤外線サーモグラフィとは、対象物が発する赤外線(熱)を可視化する技術です。
例えば、コンクリート構造物であれば、浮き・剥離・水分の浸透といった異常部は熱伝導が異なるため
健全部とは異なる温度パターンを示します。これを利用して、目視では発見できない劣化や損傷の兆候を早期に把握することが可能です。
特に、外壁や道路構造物、橋梁の点検では、打診検査や近接目視に代わる効率的な手法として
サーモグラフィ調査の需要が高まっています。
資格取得により、実務での信頼性が向上し、公共工事における入札や仕様書対応にも有利になります。
レベル1は基礎的な段階ですが、「正しい機器の選定」「適切な条件での撮影」「異常の識別と簡易的な評価」ができるスキルとして認定されます。
資格取得のきっかけと今後の展望
私は建設コンサルタントの道路部門に登録している測量会社に勤務しており
日々、道路台帳作成や境界確定、地形測量などの業務に携わっています。
その中で、補修や更新を見据えた点検業務のニーズが着実に高まってきたのを感じていました。
特に、サーモグラフィとドローンを組み合わせた点検手法には大きな可能性を感じています。
高所や狭隘部、危険箇所など、人が近づけない場所の点検をドローンで撮影し、その赤外線画像をもとに解析することで
従来の点検業務の「安全性」「スピード」「精度」が大幅に向上します。
そのため、「まずは資格取得から」と考え、サーモグラフィの基礎を学び、今回レベル1試験に合格しました。
非破壊検査や画像解析の知識は、自分自身の技術力向上だけでなく、会社の新たな事業の柱としても活かせると確信しています。
レベル2取得を目指して
現在は、さらに一歩進んで「サーモグラフィ レベル2」の資格取得に向けて、毎日少しずつ勉強を進めています。
レベル2では、異常の特定・定量評価や報告書作成における技術的判断、検査責任者としての知識が求められます。
つまり、レベル2は「現場責任者としての判断力」が評価されるステージです。
公共事業では、「技術者の保有資格」がプロポーザル評価や入札要件に組み込まれるケースも増えており
資格が仕事を広げる武器になることは間違いありません。
ドローンとサーモグラフィの融合で切り拓く未来
私のもう一つの強みは、「ドローン操縦ライセンス(一等無人航空機操縦士)」を保有していることです。
これにより、サーモグラフィカメラ搭載ドローンでの点検業務を自社でワンストップで提供できる可能性が出てきました。
今後は以下のような取り組みを進めていく計画です:
- 橋梁や法面、擁壁などの赤外線点検業務の受注体制の構築
- 点検結果の可視化・報告書作成のテンプレート整備
- 自社内でのデモ・試験的運用によるノウハウ蓄積
- 建設コンサルタントや自治体との連携強化
このように、赤外線技術 × ドローン × 測量という掛け算は
地方の中小企業でも十分に勝負できる領域だと考えています。
まとめ
インフラメンテナンスの需要は、今後ますます高まります。
単なる測量業務から一歩踏み出し、「点検・評価・提案」まで担える技術者として成長することで
自社の付加価値を高め、地域社会に貢献できる存在になれると信じています。
まずは取得したサーモグラフィレベル1を武器に、さらに高みを目指してレベル2へ。
ドローンや非破壊検査技術を活かしながら、
未来のインフラ点検に貢献する新しい技術者像を築いていきたいと考えています。
(愛徳コンサルタント株式会社)