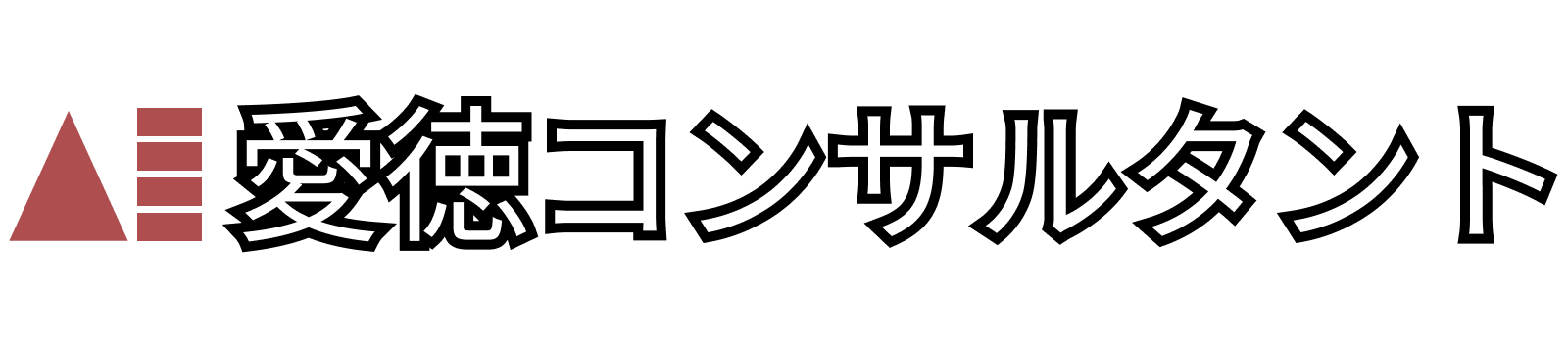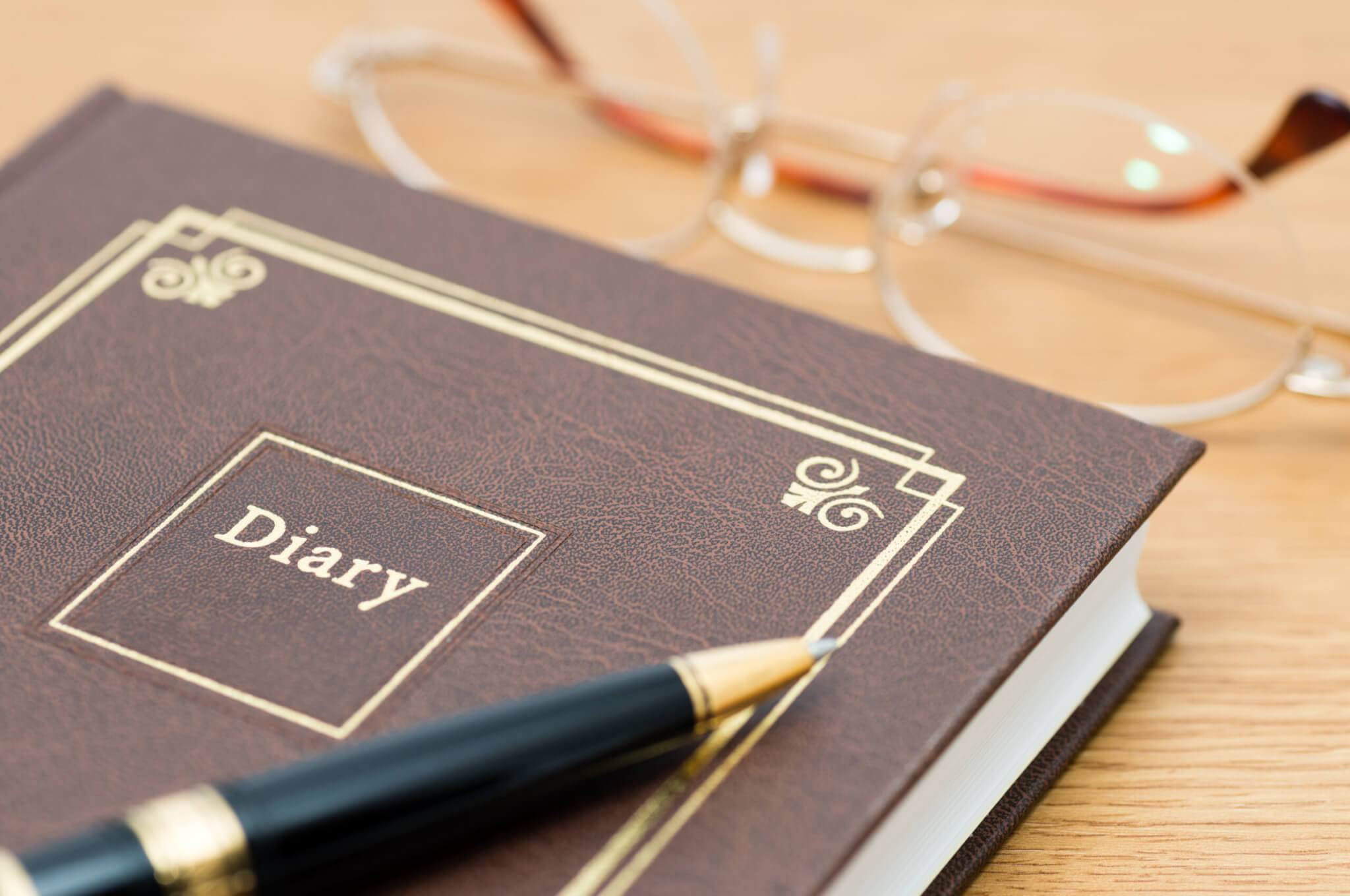このたび、地籍工程管理士の検定試験に合格しました。
本記事では、この資格を取得するための条件と難易度、取得すると何ができるのか、
初受験の体験談(過去問がない・記述式が多い驚き)、愛知県の地籍調査の進捗、今後の見通しを測量会社の現場目線でまとめます。
地籍工程管理士とは?2項委託の工程管理・検査をリードする専門家
地籍工程管理士は、国土調査法第10条第2項に基づく民間委託(いわゆる「2項委託」)の地籍調査において、
工程管理と検査を中心に、地籍主任調査員等を指導する立場の専門技術者です。
研修と検定試験を経て、(公社)全国国土調査協会会長より資格が付与され、登録のうえ活動します。
民間側で品質・工程の中核を担い、事業の適正かつ迅速な推進に資する役割が期待されています。
取得条件(受講・受験資格)と流れ
受講・受験の主な条件(要点)
- 地籍主任調査員の資格を有し、地籍調査や類似業務に3年以上従事した実務経験があること。
- 地籍工程管理研修を受講すること(過去受講者も受験可)。
その後地籍工程管理士検定試験に合格し、所定の手続きを経て登録。
実際の申請では、登録証の有効性や実務経歴の証明など確認事項が細かく定められています。
手続きのステップ
- 地籍主任調査員(有効な登録)+3年以上の関連実務
- 地籍工程管理研修の受講
- 検定試験に合格
- 地籍工程管理士として登録・更新(規則・更新研修に基づく)
※最新の募集・日程・様式は(公社)全国国土調査協会の案内をご確認ください。
2025年度は「第13回 地籍工程管理研修・地籍工程管理士検定試験」が告知されています。
難易度の肌感:過去問題なし/記述が6割ほど“わかる”を“書ける”に変える訓練が要
今回は過去問題が公開されておらず、初めての受験でした。
さらにマーク式ではなく、体感で6割ほどが記述式。いわゆる「用語を知っている」だけでは点にならず、
工程管理や検査の考え方を、設問の前提に即して“自分の言葉で組み立てて書く力”が問われます。
正解の方向性は分かっていても、専門用語の漢字で手が止まる悔しさも……。
以後は毎日、技術用語の書き取りと短文アウトプット(100〜150字)の練習を続けることにしました。
参考までに、関連資格(地籍調査管理技術者)では選択式+記述式の構成で、
法令・一筆地・工程管理・測量の4科目という体系が示されています。
「記述で説明する力」が重視される点は共通と見てよいでしょう。
学習のカギ(私見)
- 工程管理の全体像(A〜H工程)を、検査・記録・照合の要点まで流れで語れるようにする。
- 規程・要領に沿う“根拠ベース”の記述に慣れる(例:閲覧前後の検査、誤り等申出の処理、数値情報化の扱い等)。
- 法令・準則の条文キーワードは、**“どの工程の何を担保する条文か”**の紐づけで覚える。
漢字対策は軽視しない(「筆界」「認証」「照合」「閲覧」「準則」…等、頻出語の手書き)。
もっていると何ができるか?現場での“効きどころ”
地籍工程管理士のコアは、工程と品質の両輪をルールに基づいて回すことです。
現場では次のような“効きどころ”があります。
- 工程計画と関係機関連携の主導:登記所・公物管理者との事前協議、広報・住民説明の段取りを含む「A・B工程」の要所を、準則の趣旨に沿って設計する。
- 検査体系の構築・運用:照合点検率や出来映え検査、閲覧前後の検査、誤り等申出処理まで、検査記録の全数管理を徹底し、認証申請へスムーズに繋げる。
- 数値情報化の確実な実装:地籍調査成果の数値情報化実施要領に則り、GIS等で活用可能な形で行政DXに資する成果を整える。
- 主任調査員等の指導:2項委託の品質を底上げするため、教育・点検・是正のPDCAを日常化する。
結果として、自治体側の認証プロセスが円滑になり、トラブル対応の初動が早く、再作業や差戻しの低減につながります。
工程と品質の要点が記述で語れる=実務で“使える”設計図を持っている、ということだと感じます。
初受験のリアル:過去問なし・記述中心で感じたこと(体験談)
- 出題の粒度:単なる暗記ではなく、工程管理の「判断」を言語化する問題が印象的。例えば、住民説明と関係機関調整のタイミング、閲覧対応と誤り等申出処理の留意点、認証申請までの記録整備……といった「運用の整合性」を問う設問。
- 時間配分:記述比率が高い分、メモ→骨子→清書の3段構えが必要。最初の10分で設問の“想定読者”(実施者か検査者か、など)を掴むのがコツ。
- 言葉の精度:たとえ内容が合っていても、用語の漢字で減点されかねない手応え。**毎日10語の“手書き”**は地味に効きます。
情報ソース:実施要領・規程細則・ガイドブックは条文番号や図表も含めて読み込む価値大。現場の癖だけで書くと、条文の要件を外しがちです。
愛知県の地籍調査——進捗状況のいま(数値と地図)
全国の進捗(令和6年度末)は、地籍調査対象地域で53%、優先実施地域で81%に達しています。
都市部(DID)や山村部(林地)は遅れがちで、重点化が続いています。
愛知県の進捗(令和5年度末)は、
- 県総面積:5,173.21 km²
- 要調査面積:4,924.79 km²
- 調査済面積:666.92 km²
- 進捗率:13.5%(全国平均に対して依然低位)
市町村別の状況や進捗率は、地籍調査状況マップから確認できます。
※愛知の進捗率は県公表の令和5年度末実績です。
最新の市町村別情報は、国の状況マップ(令和7年度6月時点の実施状況、令和6年度末時点の進捗率を掲載)で更新されます。
2025年度(令和7年度)の愛知県の取組——どこで、何を進めるのか
愛知県は、令和7年度の地籍調査事業計画を公表しています。
岡崎市・瀬戸市・半田市・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市など、県内広域で調査が進められます
(※地区名は計画に明記)。当社の主業務エリア(西三河)でも、豊田市・安城市等で着実に前進していく計画です。
計画は国土調査法第6条の3に基づき定められ、対象地区・期間・公示日等が明記されます。
自治体・受託者・住民が「いつ・どこで・どの範囲をどう進めるか」を共有する骨格となります。
「これから」の地籍調査——第7次十箇年計画の文脈で
国は第7次国土調査事業十箇年計画(令和2〜11年度)のもと、
都市部(DID)や林地の遅れ解消、効率的な調査手法の導入(リモートセンシング等)、関係機関連携の強化を進めています。
中間見直しでもDID周辺2万km²整備など具体的な量的目標が示され、
成果の数値情報化と活用(行政DX・登記地図の更新・オープンデータ化)の重要性が一段と高まりました。
愛知県にとっても、災害レジリエンス(南海トラフ地震等)や都市インフラ更新の観点から、境界の明確化×データ活用は喫緊のテーマ。
県自身も、認証者検査の効率化・省力化や業務プロセスの見直しを掲げ、推進を図っています。
事業者としての私たちのコミット——工程×品質×DXで、早い・確かな成果を
地籍工程管理士として、当社は次の方針で業務品質を磨いていきます。
- 工程の見える化:A〜H工程のマイルストーン管理(協議・周知・現地作業・閲覧・認証申請)を、記録と照合率まで含めて前倒し設計。
- 検査の標準化:出来映え検査、照合点検、閲覧前後の確認、誤り等申出処理を記録テンプレート化し、“誰が見ても追える”ログを残す。
- 数値情報化の確実運用:成果の数値情報化とGIS活用を標準に。自治体のデータ利活用や登記所備付地図の更新に資する品質を担保。
人材育成と知識共有:主任調査員・技術者の**記述力(説明力)を高める勉強会を定期開催。書ける=運用できるを合言葉に。
まとめ
地籍工程管理士は、2項委託の工程管理・検査をリードする資格。
取得には主任調査員+3年以上の実務・研修受講・検定合格・登録が必要です。
試験は記述中心で、「根拠に基づく説明力」が問われます。
過去問がないぶん、規程・要領の読解+短文アウトプット訓練+漢字対策が決め手。
全国進捗は53%(令和6年度末)。愛知県の進捗は13.5%(令和5年度末)で、巻き返しが急務。
2025年度計画では県内広域で調査が動いています。
第7次十箇年計画のもと、DID・林地の遅れ解消、効率的手法の導入、数値情報化と活用が鍵。
私たちは工程×検査×DXで貢献していきます。
最後に
今回の合格は、会社としての品質と責任の約束でもあります。
早く・正確で・使える成果をお届けするため、引き続きトレーニングと改善を重ね、愛知の地籍整備に力を尽くしてまいります。
(愛徳コンサルタント株式会社)